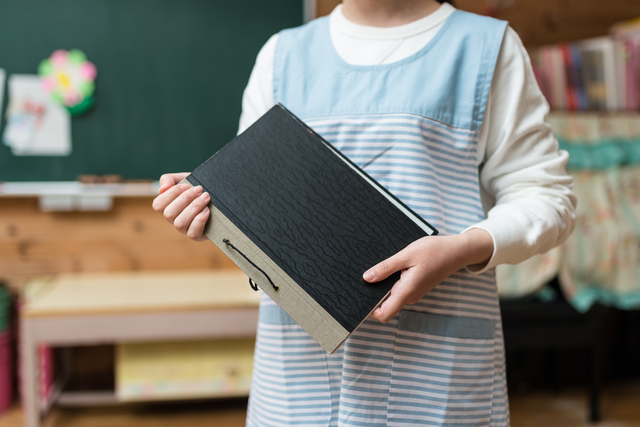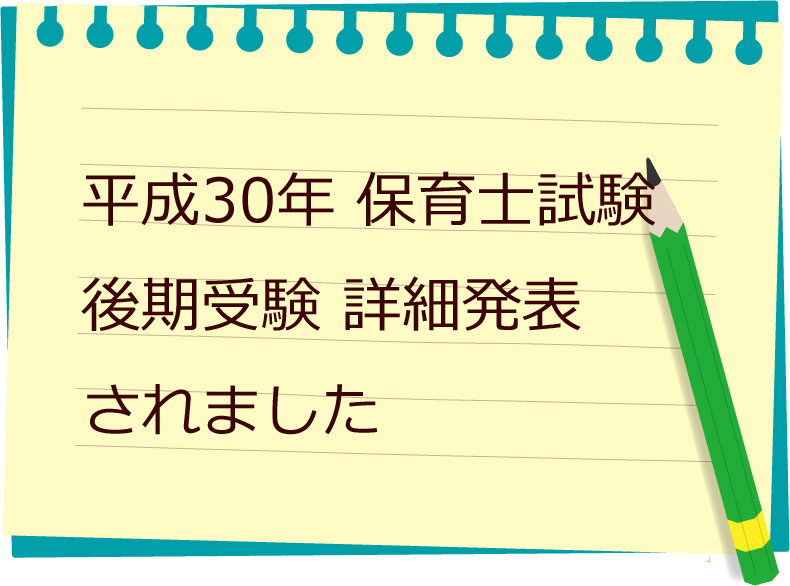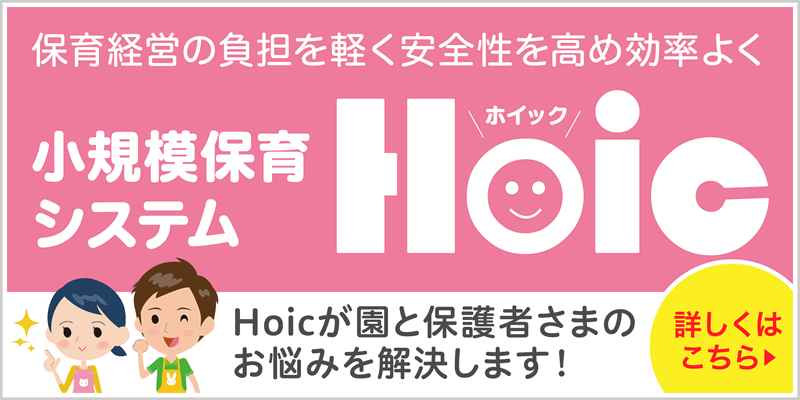大阪大学の研究チームは、三つ子など複数の胎児を妊娠した場合に、母体の負担を軽減する目的で行われる「減胎(減数)手術」について、国内初となる臨床研究の結果を発表しました。
この研究では、10人の妊婦を対象に手術が行われ、安全性が確認されたとしています。
研究チームは、手術を受けた妊婦の身体的および精神的な状態を継続的に見守りながら、今後は複数の医療機関と連携して、さらに研究を深めていく予定です。
これまで、この手術は倫理面での課題から十分な議論がなされてきませんでしたが、今回の臨床研究は、安全な実施方法や明確なルールを構築するための重要な一歩となります。
(※2025年7月13日 朝日新聞の記事を参考に要約しています。)
大阪大が初の報告、減胎手術の臨床研究、安全性と課題を明らかに
大阪大学の研究チームは、減胎(減数)手術に関する臨床研究の成果を、7月13日から開催される日本周産期・新生児医学会の学術集会で発表する予定です。
妊娠する胎児の数が多くなると、早産や分娩後の多量出血など、母体に対するリスクが大きくなるとされています
。一定数の妊婦には減胎手術が必要とされる一方で、国や専門学会による明確な指針やルールは現時点で存在していません。
このたびの研究では、学内の倫理審査を経た上で、三つ子以上を妊娠している場合、または双子で重度の合併症を抱える妊婦を対象に、2024年4月から12月にかけて同意を得た10人に対して手術が行われました。
妊娠11~13週に、対象の胎児の心臓に塩化カリウムを注入し、その後1週間にわたり、母体と胎児の経過を観察しています。
全10例で胎児の数を減らす手術は成功し、そのうち1例では一時的に心拍が戻り再手術となりましたが、研究チームは「高い確実性が確認できた」と述べています。手術対象外の胎児の生存率は約90%に達しました。
また、多くの妊婦が手術前に不安や抑うつの兆候を示していたことも明らかになりました。
手術後には多少の改善が見られたものの、不安感は依然として高い水準にありました。
今後、大阪大学は出産を終えた妊婦の心身の状態を引き続き観察しながら、今後3~5年の間に他の医療機関との連携によって、安全で標準化された手術手法の確立を目指すとしています。
すでに大阪大学病院では、減胎手術に対応する外来診療も開始されています。
研究責任者の遠藤誠之・大阪大学教授(産婦人科)は、「この手術に対応している医療機関が公にされていないことで、妊婦が後ろめたさを感じるケースもあります。
多胎妊娠の現実に向き合い、減胎手術を選択肢の一つとして冷静に考えられる社会づくりが求められています」と述べています。
減胎手術をめぐる倫理と支援体制の課題、安心して選択できる社会へ
減胎手術が日本で初めて公表されたのは1986年で、長野県の医療機関が実施したものでした。
当時、日本母性保護医協会(現在の日本産婦人科医会)は、減胎手術が当時の優生保護法(現・母体保護法)の人工妊娠中絶の定義から外れるとして、堕胎罪に該当する可能性を指摘し、「減胎手術は行うべきではない」との立場を示しました。
その後、体外受精の普及により、複数の受精卵を一度に子宮へ戻すケースが増え、三つ子や四つ子などの多胎妊娠が目立つようになりました。
こうした背景から、日本産婦人科医会は2000年、「母体保護法の枠内で手術を容認すべきだ」とする提言をまとめました。
さらに、2003年には厚生労働省の審議会も、「三つ子以上の妊娠に限り、母子の命を守る観点から減胎手術を認めるべき」とする報告書を発表し、国や学会に対して明確な基準の策定を求めました。
しかし、その後も具体的なルールの整備は進まず、現在も一部の医療機関で限られた形で実施されている状況です。
全国的な件数は把握されておらず、実際に手術を受けた妊婦や家族が罪悪感や社会的孤立感を抱えているケースも少なくないとされています。
2008年には日本産科婦人科学会が「体外受精で戻す受精卵の数は原則として1個」とする見解を示したことにより、多胎妊娠の発生は減少傾向にあります。
それでも排卵誘発剤の使用などによる多胎妊娠は一定数存在し、減胎手術を必要とする妊婦が今もいるのが現実です。
どの胎児を選択的に残すかといった倫理的な問題に加え、妊婦への十分な情報提供や同意の取り方、心理的支援のあり方についても、今後の検討が求められています。
欧米諸国では、倫理的な課題を前提としたうえで、胎児医療に精通した施設において、医学的・心理的に安全で質の高い支援を提供する体制づくりが推奨されています。
当事者の尊厳を守る体制づくりを-減胎手術の公的研究開始に期待
【斎藤有紀子・北里大学准教授(生命倫理学)のコメント】
これまで非公式に行われていた減胎手術の臨床研究が、ようやく正式に始まったことは大きな前進だと感じます。
日本では長年にわたり、この手術についての本格的な議論が避けられてきたために、手術の実施方法や妊婦への適切な情報提供、さらには当事者への心理的サポートについても、明確な基準が定められてきませんでした。
今後は、こうした状況を改善し、手術を受けた方々が社会からの偏見や差別(スティグマ)に苦しむことのないように、医療現場におけるガイドラインを早急に整備していく必要があります。