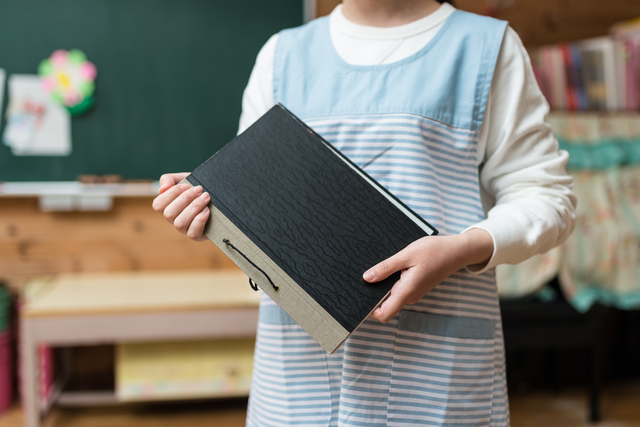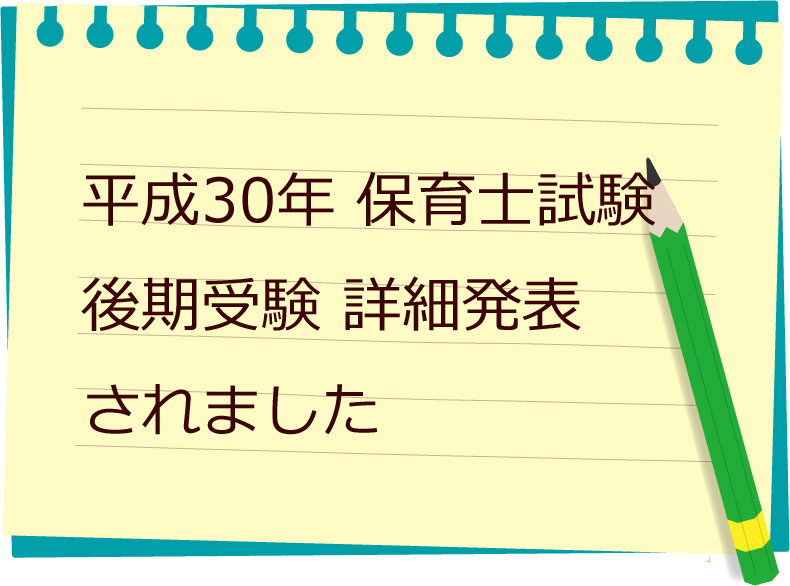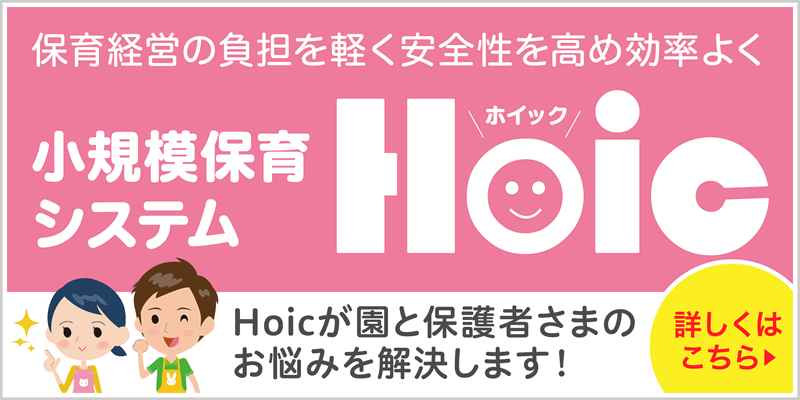子どもの権利条約が批准された後、日本社会にはどのような変化が見られたのでしょうか。この条約を締結した各国や地域の取り組み状況を審査する「国連子どもの権利委員会」の委員を務めておられる弁護士の大谷美紀子氏にお話を伺いました。
(※2024年12月11日 朝日新聞の記事を参考に要約しています。)
子どもの権利が認められるまでの歩みと課題
子どもに関する国際社会の認識は、条約が採択される以前まで、子どもは特別な保護を必要とする存在として扱われてきました。
1959年に国連で採択された「児童の権利に関する宣言」においても、子どもは身体的および精神的に未熟であり、社会が守り支えなければならない存在と位置づけられていました。
しかし、この条約の成立により、子どもは単なる保護の対象ではなく、自立した権利の主体であると公式に認められたことは、大きな意義を持つものです。
一方で、国際社会において子どもの権利が常に最優先とされる状況には至っていません。
条約を締結した国々や国連は、子どもの権利を守るためにさらに真剣に取り組む必要があると考えられます。
子どもの権利保護に向けた日本の30年の歩み
日本は、子どもの権利条約を批准してから30年間で、4回にわたる国連子どもの権利委員会の審査を受け、数々の問題点を指摘されてきました。
その中には改善された点もいくつかあります。
たとえば、2011年に制定された家事事件手続法では、離婚調停や面会交流といった家庭裁判所での手続きにおいて、子どもが意見を表明することを支援する「子どもの手続代理人」という制度が設けられました。
また、2014年には、児童ポルノに関する法改正が行われ、単純所持も処罰の対象とされました。
さらに、2019年および2022年には、児童福祉法や児童虐待防止法、そして民法の改正によって、親が子どもに対して持つとされてきた「懲戒権」が削除され、体罰が明確に禁止される重要な一歩が踏み出されました。
子どもの権利保護に向けた「こども基本法」の意義と今後の課題
日本政府はこれまで、子どもの権利条約と国内法の整合性を確認するにとどまり、総合的な法律を制定してきませんでした。
しかし、2022年に「こども基本法」が成立し、日本もようやくスタートラインに立ったと言えます。
これからは、子どもの権利を守るための仕組みとして、国の法律や予算配分を子どもの権利の観点から検証し、政府と異なる立場から調査や提言を行う国レベルの専門機関が必要です。
日本国内における法律や制度の課題を解決するためにも、子どもの権利に特化した独立機関の設立が不可欠であると考えます。